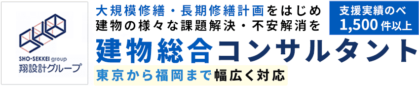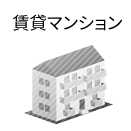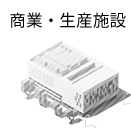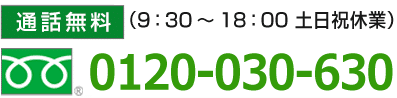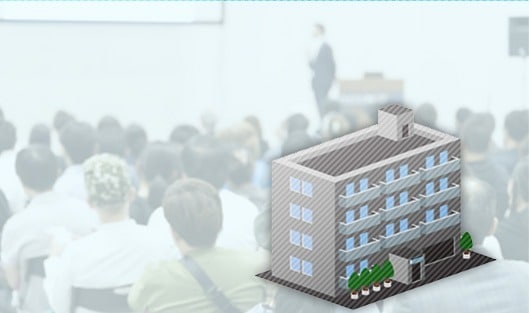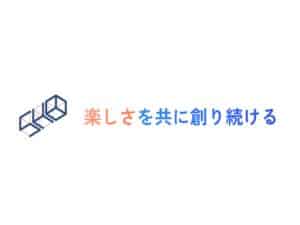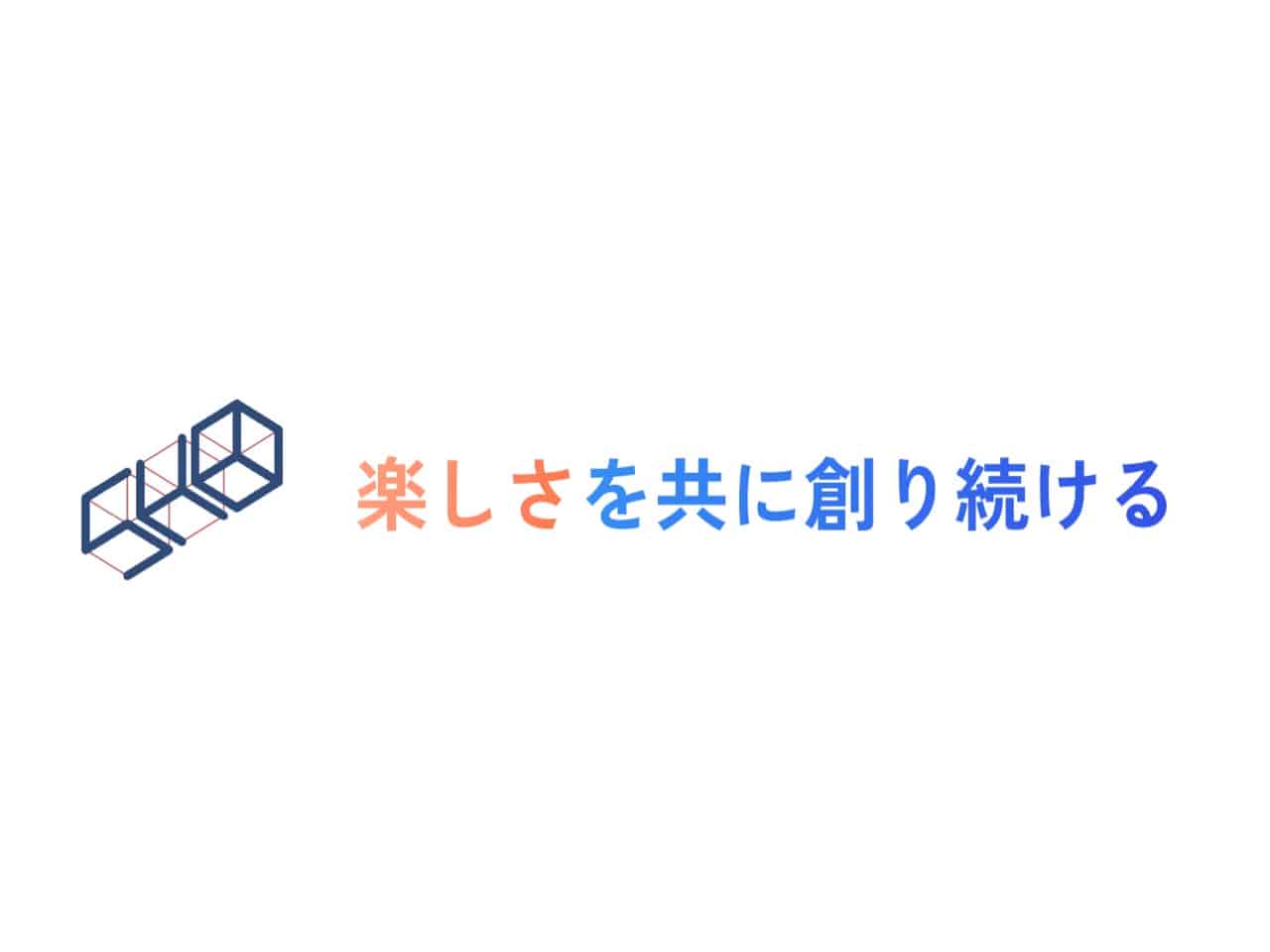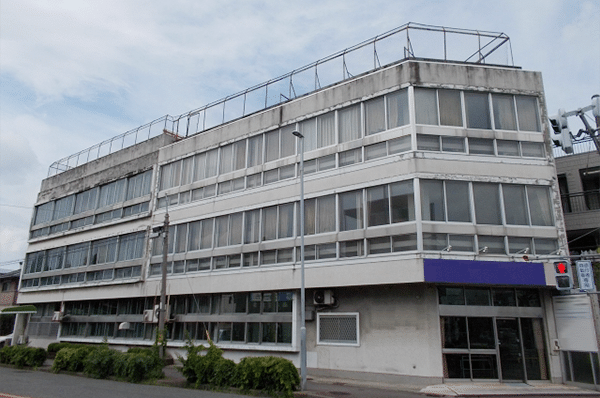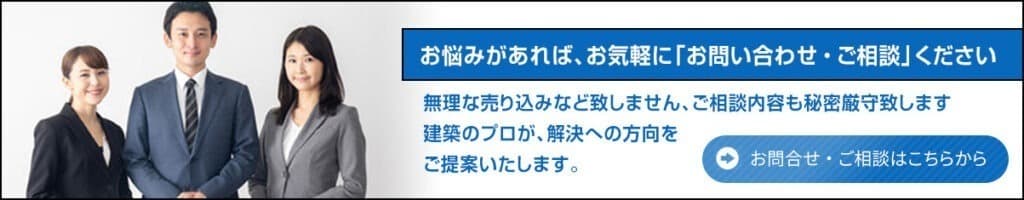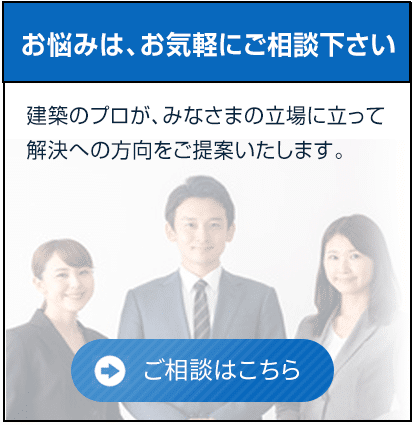耐震補強工事で1世帯でも反対されたら工事はできないのでしょうか?
東日本大震災のような大規模災害が契機となり、マンションからも耐震診断の問い合わせや、災害対策としての調査依頼が増えています。いうまでもなく安全はマンションにとって最重要事項のひとつですから、それ自体は良いことなのですが、専門家の感覚からいえば、耐震診断に対する誤解は多いようです。
第一は耐震診断についての誤解です。耐震診断によって、建物が安全になるわけではないという事実の認識が欠けていることがままあります。
耐震診断の結果とは、それぞれのマンションの耐震性を過去の地震被害から確率論的に判断した安全性を数字として明らかにすることです。実は経験を積んだ技術者であれば、建物の構造設計図書(設計図)を見れば、耐震性能の数字は推定できます。耐震診断とは、その推定値を裏付ける作業ということになります。診断には一定の意味がありますが、それによってなんら安全性が改善するわけではありません。大切なのはこの数字が出た結果に対して、どう対応していくかなのです。
診断結果で出てきた数字に対して自分たちはどう対応すべきかを、特に理事会のメンバーは十分検証しなければ意味がありません。たとえば、旧耐震基準により設計された建物であれば、安全基準を満たさないのは当然の結果です。古い設計基準で設計された建物に耐震診断を施しても、現在の基準を満たしている数値が出ることは非常にまれでしょう。しかも、重要なのは安全基準に達しないことがわかったからといっても、ほとんどのマンションでは補強工事を行うことで基準を満たす数値に改善できた事例が少ないという事実です。
重要なポイントを繰り返します。耐震診断の結果、基準を満たしていないという事実が明確化された後に、どう対応していくのかを判断することがもっとも難しいことなのです。これは大規模修繕工事以上の難題ですから、その対応を図りながら理事会をサポートしてくれる専門家の知恵を借りることが必要になってきます。
耐震補強工事の課題
耐震補強工事にはまだまだ課題が多いのが現実です。ひとつには現状ではマンションの耐震補強工事に対する補助金は決して多くありません。
しかもその補助金は指定された基準を満たすことを前提としたもので、マンションの補強に対してはあまり期待できないといっていいでしょう。その結果、資金が絶対的に不足してしまい、ほとんどのマンションは補強ができないというのが現実なのです。
目安としては新耐震設計以前のマンションに耐震補強を施す場合、一住戸当たりの平均負担額は数百万円以上にもなるといわれています。こうした理由からも、ほとんどのマンションに耐震診断を行っても基準を満たす補強はできないという現実がのしかかります。それを前提にさまざまな判断をせざるを得ないのです。
コンサルタントとしての意見を求められた場合、私たちは次のような話をすることになります。判定結果の数値が非常に低い場合は「地震が来たら覚悟をしてください」と正直なところを申し上げます。どんな覚悟が必要なのかといえば、それは「壊れることを受け入れる」覚悟です。耐震基準値を満たさないマンションは、建物が地震で大破したり、中破したりする可能性が高いことは間違いありません。中でも考え得る最悪のケースは、マンションそのものが崩壊してしまうことです。
崩壊とはつまり建物がつぶれたり、倒れてしまう状況ですから、居住者の方々が生命を失うことを意味しています。
そのような条件が明らかになった場合、最良の選択は生命を守ること、すなわち崩壊を防ぐことに尽きます。補強の有無にかかわらずマンションが壊れてしまうのであれば、いずれにせよ震災後に居住できなくなるということは受け入れざるを得ません。そう考えると、まず何を置いても地震で人が死なないような人命の確保を第一に考え、補強だけは行うべきとわかるはずです。
「地球」対「マンション」という関係で地震という条件を考えれば、マンションに勝ち目はありません。そこではどう負けるかを考えていくべきなのです。建物を守るための補強ではなく、人命確保の補強手法を考え、目指さなければなりません。それによって比較的少ない資金でも様々な補強を実施できる可能性が出てきやすくなります。
その段階をクリアしたうえで、さらに追加資金が捻出できるのであれば、次に建物大破による二次被害に備えていくべきでしょう。
地震に対する準備と防災
建物は壊れるということを理解し、そのうえで安全を確保するのであれば手法はあります。たとえば火災を発生させないような対策、落下物による人的被害の防止、建物の部分崩落の可能性のある部位の部分補強、部屋に閉じ込められないような玄関ドアの改修、設備機器の耐震化、エレベーターの閉じ込め防止装備、緊急防災品の保管などです。
さらに忘れてはならないものに、住民同士の助け合い体制があります。それを確立させる手法は、日常的なコミュニケーションの積み重ねのほかにありません。おわかりのように日常的なコミュニケーションとは大規模修繕工事などを通して住民間の関係強化や情報共有を図ることから生まれてきます。
また、防災を考えることは安全を考えるということと同様でもあります。地震防災だけでなく、そこには火災防災、侵入防災、衛生防災など多数の項目が関連してきます。マクロな目で防災をとらえて対応することが大切であり、さらにそれらすべての基本にあるのが住民の協力という要素です。
真の「防災」と「コミュニティ」は同じ目的を持つという点から切っても切れない関係にあります。これらも理事会がリードするマンションの生活価値向上の取り組みの結果から生まれてくるものにほかならないのです。
マンションの防災でお悩みの方はこちらをご覧下さい
まずはマンション全体で防災についての意識を持つことがスタートです。専門家による防災全般の調査を行い、実態を把握することが重要です。
起こる前に準備をしましょう。準備をしておくかしておかないかで、大きな差がでます。
翔設計では耐震補強や水害対策、災害時マニュアルの作成等、防災に関する様々な業務を行っておりますので、ぜひご相談ください。