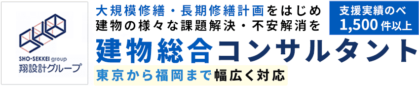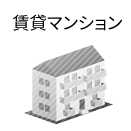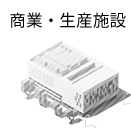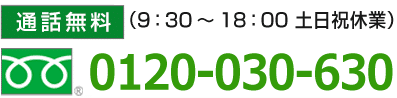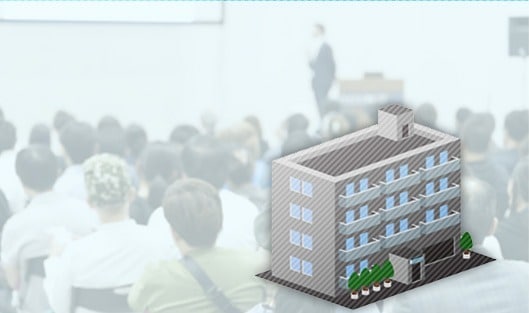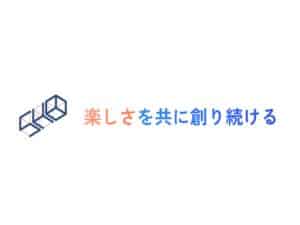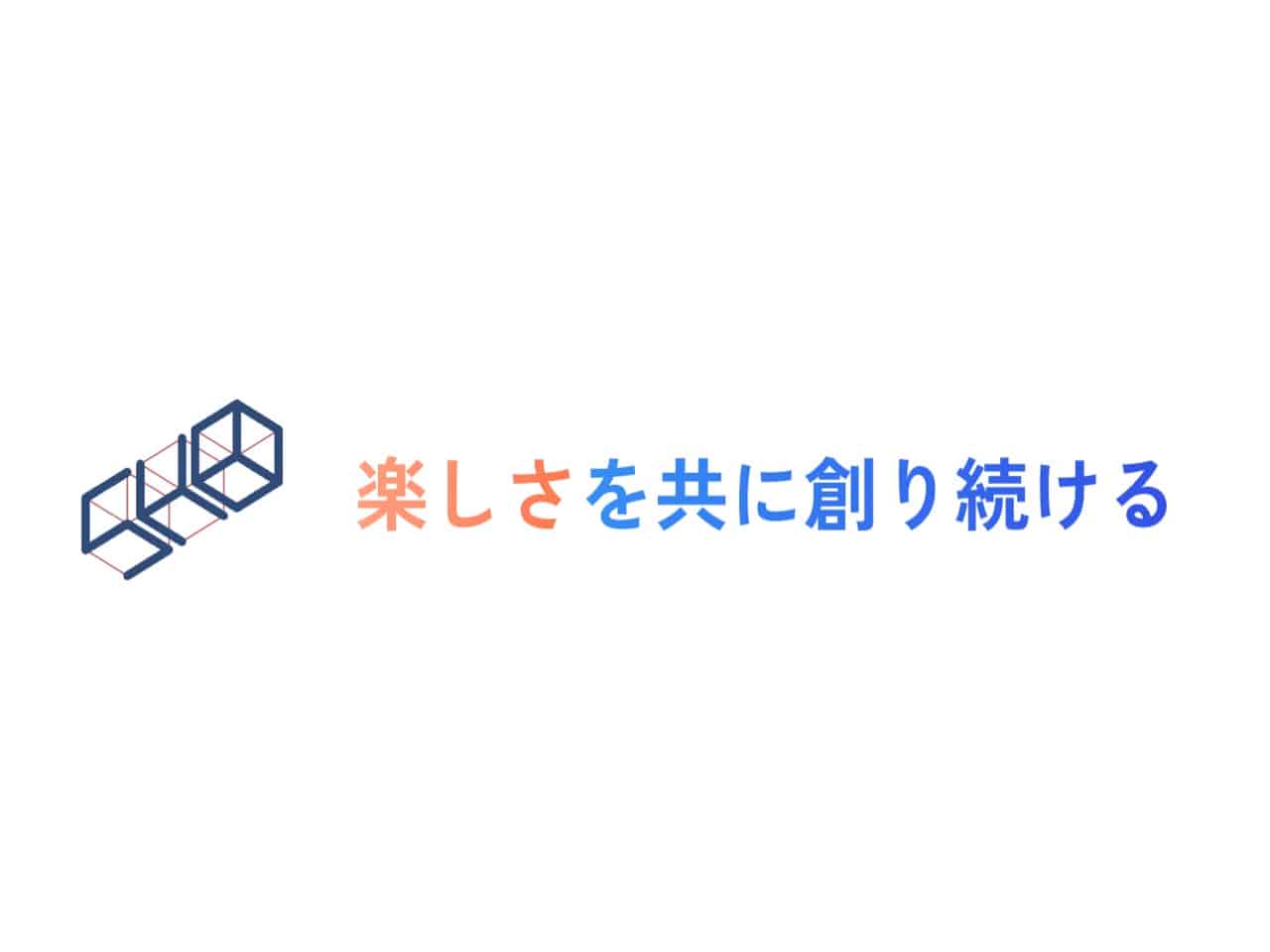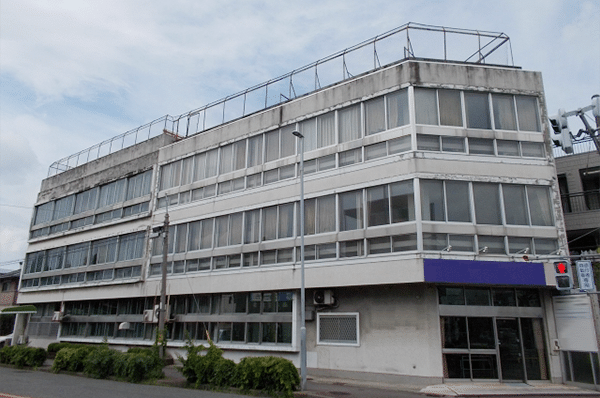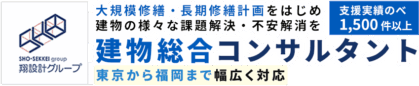第45回「高経年建物の課題と解決手法」セミナーレポート
過去行いました翔設計主催のセミナーについて、その概要などをまとめています。セミナーに参加を検討されている、弊社サービスをご検討中であるという方は、この内容をご参考にして頂ければ幸いです。
セミナー開催情報
- タイトル:第45回セミナー第一部「高経年建物の課題と解決手法」
- 日時:2023年01月21日(土) 14:00~16:00
- 会場:株式会社翔設計1F
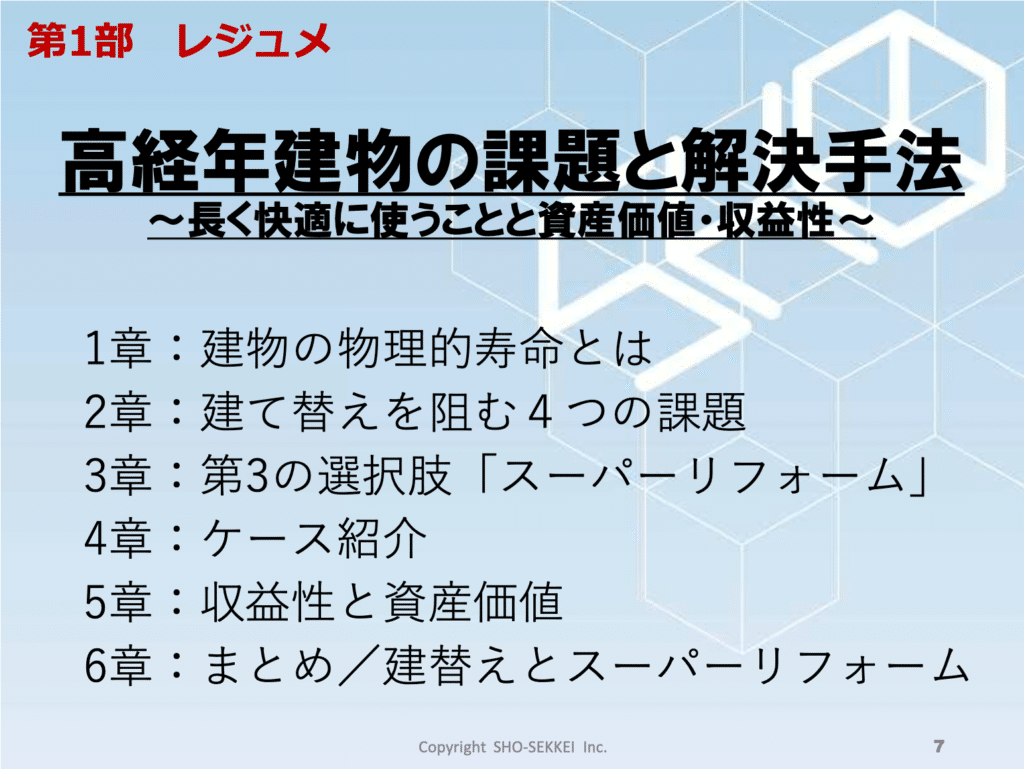
セミナーの概要
- 躯体は長持ちだが設備インフラは時代遅れに
コンクリート自体は強いが、配管や電気設備、通信などが物理的・社会的・機能的に劣化する。 - 分譲マンションは合意形成が最大のハードル
建て替えには5分の4以上の合意が必要となる。 - 実際には法規制や施工難、費用がネック
様々な法規制のクリア、施工条件・工事費用の高騰などハードルは高い。 - スーパーリフォームなら既存の駆体を生かしつつ、専有部も含め、設備・インフラを更新し、耐震性能も向上
建て替えほどお金がかからず、建物全体のフルリニューアルが可能、CO2排出を減らし、地球にも優しい。 - 早めの“終活”を!
マンションの終活には選択肢があり、方向性が定まるまではかなりの時間を要するため、早めに検討を始める必要がある。専門のコンサルタントに相談し、段階的に検討を進めていくことを推奨。
老朽化が進むマンションやビルなど、高経年建物が増え続ける中、どのように再生・延命を図り、資産価値を維持するかが大きな課題となっています。今回のセミナーでは、建物を取り巻く環境や再生のための具体的な方法、そして実際の事例までを紹介します。
はじめに:高経年建物が増え続ける背景
近年は築年数の経過したマンションやオフィスビルが増加し、改修や建て替えの必要性が急速に高まっています。
ただし、分譲マンションと賃貸物件とでは、所有形態や合意形成の進め方が異なるため、再生や建て替えに向けた検討は大きく異なります。
特に分譲マンションは管理組合の合意や法律上の制約が多く、容易に建て替えに踏み切れない実態があります。
そこで、本セミナーでは「建物の終活」という切り口から、建築の専門家が高経年建物の課題と解決手法を整理し、複数の選択肢を紹介しました。
高経年建物の課題と再生手法
1. 建物の寿命と設備インフラの劣化
コンクリートは適切に保護されていれば非常に長持ちします。一方、給排水管・電気系統などの設備は比較的早い段階で劣化します。
- 給排水管:築40年を超えると漏水リスクが顕在化しやすい
- 電気設備:古いマンションは全体の容量不足(アンペア数)や配線の老朽化
- 通信環境:地上波のデジタル化や高速通信に追いつけないケース
- 断熱や防犯性能:地球温暖化や防犯ニーズに対応できていない
こうしたインフラ面の課題が蓄積すると、大規模修繕だけではカバーできない改修が求められるようになります。
2. 建て替えを阻む4つの課題
実際に「建て替え」を検討する際に立ちはだかる4つの壁があります。
- 法的制約
- 日陰規制や容積率など、現行法規の制約により、現状より小さな建物になる既存不適格の問題
- 容積率の緩和を受けられる条件に合わず、メリットが得られないケース
- 施工性の問題
- 重機が入れない立地、足場が組めない密集地、アーケード商店街などで解体や建築がそもそも難しいケース
- 工事費用が莫大になるリスク
- コスト・収益性
- ウッドショックや鉄骨価格の高騰など、資材費の上昇
- 不動産市況や世界情勢の影響で事業費が膨らむ
- 建て替え後の販売価格や容積緩和の有無によって収支が左右される
- 合意形成の難しさ
- 分譲マンションでは5分の4以上の合意が必要
- 資金負担や工事期間の長期化、外部所有者の理解を得る必要性
これらがすべてクリアできないと建替えには進むことができず、一方で進む劣化に対応できず、売却して解体するという結末もあり得る。しかし解体にかかる費用をどう負担するか、管理組合をどう解散するかといった新たな問題も生じるため、慎重な検討が必要です。
3. 第三の選択肢「スーパーリフォーム」
建て替えが難しいケースの代替案として「スーパーリフォーム(一棟リノベ)」があります。
→ スーパーリフォーム(一棟リノベ)の詳細はこちらもご覧下さい
- 躯体を残し、設備や内装、場合によっては耐震補強を含めてスケルトン状態から刷新する大規模改修
- 解体・新築と比べてCO₂排出量を7割削減できる試算もあり、SDGsの観点でも注目
- 専有部を含め全面改修するため大規模修繕より大きな費用負担や工事期間を要するが、建替えと比べるとハードルは低い
一方、既存の構造から大きく外れる間取り変更が難しかったり、法制度が明確に整備されていない点も課題。それでもビルや賃貸マンションでは成功事例が増え、分譲マンションでも導入を検討する動きがあります。
Q&A
Q1. 排水管の寿命と交換タイミング
給排水管は主に「縦管(共用部)」と「横管(専有部)」に分類されますが、更新のタイミングにズレが発生しがちです。
近年は築40年以上で専有部の漏水頻発が深刻化しており、国交省ガイドラインでも同時交換をすすめる流れがあるようです。
区分所有者任せにすると特に専有横引き管からの漏水事故発生リスクがあるため、管理組合として専有部を含め、マンション主体で一体的に計画する必要性があります。
Q2. 築50~60年のマンションは売買可能か
実際には売買実績もあるものの、住宅ローンを組む際に制限がかかったり、頭金を多く求められたりと金融機関の対応に差があるようです。
現状では、スケルトンリフォーム済みでも建物全体の耐震や設備更新が不十分な場合が多く、買主側に詳しい情報が伝わっていない点が課題とされました。
Q3. 管理会社では同様の検討ができないのか
管理会社は日常的な管理業務が主であり、建て替えやスーパーリフォームといった再生プロジェクトそのものを主導する立場にはないことが一般的です。
大規模改修や建替えの意思決定には、建築や不動産市場、金融面での総合コンサルティングが必要で、管理会社の役割を超える分野が多々あります。
Q4. 修繕積立金が足りない場合
値上げを避けながら工事費を抑えるには、分割発注方式や補助金・助成金の活用などがあるでしょう。
ただ、根本的には国交省も「修繕積立金の水準は想定より足りない」と示しており、将来的な修繕や改修を見越して早期に積立金の増額を図る必要があるでしょう。
おわりに
老朽化した建物を再生し、長く快適に使うには「早めの計画と準備」が欠かせません。建替えが可能かはマンションの条件によって大きく異なり、まだまだ建替えは進んでいないのが現実です。
建て替えと修繕の“中間”にあたるスーパーリフォームが新たな選択肢として考えられます。
今後のアクションとしては:
- 必要に応じて、建築・不動産・金融の総合コンサルタントやPM企業に相談する
- 現状の課題を整理し、法的・コスト面を検証し「複数の再生シナリオ」を検討する
- 区分所有者全体で情報を共有し、合意形成プロセスを早めにスタートさせる
将来的にどうするか明確に決まっているマンションは多くありません。まずは、だからこそ、建物の寿命を正しく把握し、将来的な選択肢の検証とそれに伴う準備を早めに進めることが安心につながります。